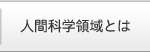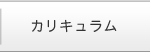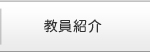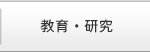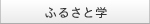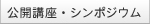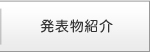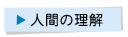国際的な視野から、健康や看護の問題について考え、国際社会でも活躍できることを目標に設けられている
科目群です。
そのための設備として、LL教室を設置し、英語だけでなくドイツ語、中国語、ロシア語も学べるように
しています。

「10年勉強しても上達しない日本人の英語」、「英会話と日本人の奇妙で複雑な関係」、「国際化時代、マルチメディアの時代における英語」、「看護大学における英語学習」等々の問題をできるかぎり視野に入れた上で、現在私たちに与えられている状況の中で、どういうことがどの程度可能なのかを考慮して、少しでも意味のある時間にしたい。
英語Iを踏まえ、さらに英語力の基礎の強化を図るとともに、平易ながらも内容にすぐれた英文を講読し、英語と日本語の本質的違い、英米人と日本人の感性の違いなどにも言及し、広く、深い読解力を養成するきっかけをつくりたい。
この授業は、前半3分の2は、ビデオやテープを使用し、聞き取り能力や対話能力を身につける授業です。その目的は、実際にドイツへ旅行しても不自由なく話せるだけの会話力を身につけること、また能力のある人は、それ以上の対話できるための十分なドイツ語力を養うことです。後半3分の1は、医学または看護に関する会話や記事の読解を通して、ドイツ人のものの考え方と日本人のそれの相違を認識することです。そのために異文化コミュニケーション理論に基づき、日本語とドイツ語/英語のコミュニケーション文法の相違や日本人とヨーロッパ人の言語行動の相違を認識してもらいます。したがって、私の授業は異文化コミュニケーション・ドイツ語教育です。授業形態は、ビデオやテープで聞き取りを行うと同時に、毎時間、ペア練習、ロールプレイなど参加者同士の発話が中心になります。
中国語の基礎篇として、入門者が習得すべき基本的な学習事項を学び、会話中心の学習を通じて自然に基礎が身に付けることを目指す。
また、中国の文化にも触れ、国際的視野を広げること。
ロシア語はユーラシア大陸のほぼ北半分を占める大国ロシアの母国語であり、「独立国家共同体」の民族コミュニケーション用語でもあります。将来とも、日本とは密接な交流が必要とされる隣国です。簡単な日常会話を中心とした実践的ロシア語の能力を養うことを主眼とし、同時に必要な文法を学び、さらに、すぐれたロシア文化や生活実体にも触れる。
ここでも基本は英語の基礎力の強化である。それに加えて、少し応用的な要素も取り入れた講読や英作文にも取り組んでみたいし、看護現場における英語表現なども取り入れてみたい。
1.英語の認識能力よりむしろ英語での表現能力を培うこと。
2.看護婦(士)に必修の基本的な英語の語彙を習得すること。

英語IVは選択科目であることを考慮し、これを受講する学生各自の要望に合わせた形での学習を進めたい。
看護専門職を目指すひとにとって、必要な英語の文献を探しだし、理解し、それを活用していくことの重要性はあらためて言うまでもないことと思う。本科目はそうした点についての基本的能力を養成することを目的とする。